コラム


たったC値0.1で、こんなに違う!新築住宅で体感する驚きの高性能

住宅性能に関する指標の一つにC値があります。
何を表す数値なのでしょうか。
この記事では、わずかな差でも違いが出る、新築住宅におけるC値について解説していきます。
C値とは
C値とは、建物全体に対してどれだけ隙間が存在するかを表す数値です。
C値=住宅全体の総隙間面積÷気密測定床面積で計算されます。
総隙間面積とは、たとえばガラス窓やドア、換気口やコンセントなど住宅にわずかでも存在する小さな隙間の合計面積です。
隙間量や気密量を厳密に測定したうえで計算されます。
・C値が小さいほど気密性が高い
C値が小さくなるほど、建物の隙間の総量が少ないことを意味し、気密性が高い住宅と評価することが可能です。
たとえば、昔ながらの日本の木造住宅は、隙間風がひどく、冬が寒いとよく言われています。
戦前からあるような住宅や戦中、戦後に建った木造家屋であれば、C値は10.0ほどあります。
その後に建てられた一般的な木造住宅で5.0程度、現在は撤廃されていますが、国が省エネ基準などを定めた時期以降に建てられた木造住宅であれば2.0~2.5程度となります。
・C値のイメージ
C値を数字で見てもイメージしにくいと思いますので、ハガキで考えてみましょう。
よくある一般的な規模の住宅30坪のケースで比較してみます。
C値5.0ならハガキ3.3枚分相当の隙間、C値2.0でハガキ1.3枚分相当の隙間、C値1.0でハガキ0.6枚分相当の隙間、C値0.5でハガキ0.3枚分相当の隙間です。
C値5.0と0.5を比較するだけでも、かなりの違いがあることがわかりました。
スーパーウォール工法の家
一般的に高気密住宅と呼ばれるのは、C値2.0以下と言われています。
これに対して、スーパーウォール工法の家ではC値1.0が基準とされています。
これからムラジ建設で建てる新築住宅のC値の目標は最低でC値0.3以下を目指しています。
標準的なスーパーウォール工法に加えて、断熱窓や断熱ドアなどをプラスすることで、さらにC値を小さくすることも可能です。
実際に建築された住宅については、必ず気密測定が実施されます。
住宅の構造体とサッシやドアなどの開口部の工事が完了した段階で、気密測定を実施してC値の算出がなされます。
そのうえで、設計時の熱計算により算出された温熱性能と外皮性能と、実際に測定した気密性能の数値を確認できる独自の性能報告書が発行されるので、マイホームの気密性が客観的に理解できるのがメリットです。
まとめ
C値は気密性を表す数値で、数値が小さいほど気密性が高く、冬も暖かく過ごせます。
同じ注文住宅でもC値に差が出るので、C値0.3以下を目指すムラジ建設の建てる家をおすすめします!

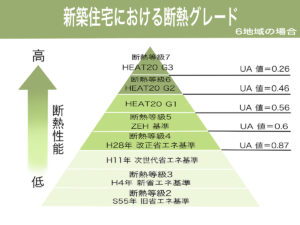




 電話でのお問い合わせ
電話でのお問い合わせ
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ